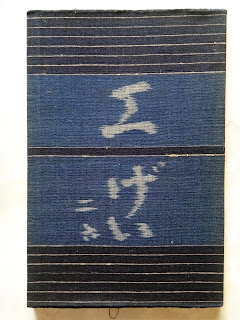イボタ蝋の続きです。
河合省三先生は1990年代から、
当時(社)農林水産技術情報協会の梅谷献二先生とともに
JICAのプロジェクトで中国でのイボタ蝋産地の調査を行われたそうです。
イボタロウムシから採取されるイボタ蝋は
現在流通しているものは全て中国産だそうです。
これは白蝋(white wax)と呼ばれます。
薬品にも使われるため、農薬などはほとんど使われていないのだそうです。
詳しくは、「生き物文化誌学会」学会誌"Biostory "第1号(2004)の
「イボタロウムシと白蝋--中国における伝統的生産技術とその検証」
(リンクは生き物文化誌学会サイト)をご覧下さい。
河合先生によれば、
「中国における伝統的なイボタロウムシの養殖は、
卵を寄主樹木に接種して雄集団の分泌するワックス(白蝋)を生産する地域と、
その接種源となる卵塊を孕んだ雌成虫=「種虫」を生産する地域とが
別地域に分かれており、その地域が数百キロも離れている、
ということからこの問題に焦点を合わせて取り組みました。」
とのことです。
蝋は雄の幼虫からしか採取できないので、
雌が同じ場所で繁殖すると蝋の採取量が減ってしまうことと、
雄雌の繁殖に適した気候も異なるのだそうで、面白いですね。
以下、河合先生が2000年8月に撮影された写真を掲載させて頂きます。
解説も河合先生のお送り下さったものを使わせて頂きます。
1. 2000年8月9日 峨眉山麓
寄主(シナトネリコ)の枝に形成された
成虫脱出前のロウ塊(もろい)を手で採取している様子
2.採取した採取したロウ塊(中に多数の虫体を含む)
3.ロウ塊を熱湯で融解
4.融けて表面に浮いたロウを掬い取る(一次ロウ)
5.丸い桶に入れて自然冷却、型取りする
6.底に沈んだ虫体を取り出す
7.虫体を細長い布袋に詰める
8.虫体を詰めた袋を再度熱湯にいれ、
棒で圧縮しながら虫体内のロウを抽出する(二次ロウ)
9.型取りしたロウ、左:一次ロウ、右:二次ロウ
いずれも原則虫体が含まれることはない
10. 一次ロウの小塊、結晶状でたやすく粉末となる
北京に工場があり(残念ながら現在は閉鎖)、
これを加工し「雪蝋」という名称で販売しています。
セラリカNODA社は元来ハゼ蝋(木蝋)の老舗ですが、
現在、木蝋をはじめ蜜蝋、
イボタ蝋のほか多くの生物ロウを伝統的な用途から近代的な用途へと発展させ、
産業として確立することを目指しているそうです。
以下、河合先生のメールをそのまま写させていただきます。
「一次ロウ、二次ロウでは組成や品質に大きな違いのあることが予想されますが、
取引の段階では区別されることはないそうですので、
このまま商品として流通するとなれば、
ロットごとに異なると云っても過言ではないかもしれませんね。
民間で敷居すべりとして用いられたものはおそらく
①の段階のものを山野から採取したものでしょう。
たぶん、枝についたまま使ったのではないでしょうか。
幼虫は秋には有翅の成虫となってロウ塊から脱出しますので
ロウ塊に虫体は残りませんが、
ロウ塊はその後ほぼ1年間、枝についたまま残っています。
製品化されたものは高価なので民間で使われることはなかったと思います。」
中国では、種になるイボタ蝋の卵は別の地区から購入せねばならない事情から
あまり利益率が高くない農業生産物であり、
コストが高すぎ、当初目指していたIT分野での利用には
こぎ着けられなかったとのことでした。
「イボタロウムシはどこにでもいる、というほど普遍的な発生は見られませんが、
時々都市の公園や街路のイボタ、トウネズミモチなどに多発することがあります。
これは都市化などによる環境悪化で、
天敵のテントウムシや寄生蜂がいなくなったためで、
カイガラムシ類に一般的にみられる現象としてカイガラムシの多発は
環境悪化の指標にも使われています。
ちなみに、昨年、皇居東御苑でもイボタに多発しているのがみられました。」
とのお言葉です。
意外と身近なところにイボタロウムシが発生している可能性もありますので、
もし見つけたら私も是非利用してみたいと思います。
貴重な情報のブログでの公開をご許可頂きました河合先生に改めてお礼申し上げます。
........................
2014年1月22日 補足記事を掲載致しました。
http://kosoken.blogspot.jp/2014/01/blog-post_22.html

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)